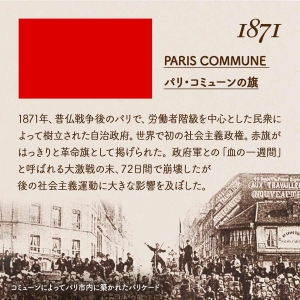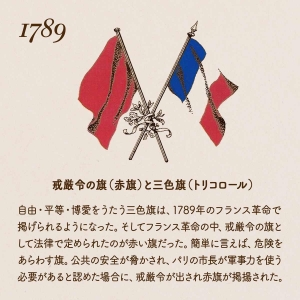ガンビア
国旗のデザインの由来と意味
2本の白い輪郭線を加えた、赤・青・緑の横三色旗。1965年、イギリスからの独立にともなって制定されました。
赤は太陽とサバンナ、青はこの国を東西に貫くガンビア川、緑は森林をあらわし、白の輪郭線は統一と平和をあらわすと同時に、ガンビア川の両岸を走る幹線道路でもあるといいます。政治的な色を避けて、ガンビアに広がる豊富な自然を反映したデザインの国旗です。
紋章や国旗のデザインの基礎となる紋章学では、紋章に使う色は、青・赤・緑といった「カラー(原色)」と、黒・白・黄といった「メタル(金属色)」などの区分に分けられていて、同じ区分にある色は隣り合わせで使ってはいけないという原則があります。ガンビアの国旗の青を挟む2本の白線はその原則にのっとって引かれたものだといわれています。
ガンビアは、セネガルにくさびを打ち込んだように、三方をセネガルに囲まれた飛び地的な国土を持った国。セネガルとの経済的結びつきが極めて強く、1982年からは軍事・経済面での一体化を目的とした緩やかな国家連合、セネガンビア連邦を成立させましたが、経済格差や利害対立などから両国の関係が悪化し、1989年に解体しました。
国章は、カラハリ砂漠の砂をあらわす白い盾型紋章。工業をあらわす3つの歯車、川をあらわす3本の青い波線、牧畜をあらわす牛の頭、盾の左右には象牙とモロコシを掲げた2頭のシマウマで構成されています。下のリボンに記されているのが、「PULA(雨、雨よ降れ)」。
また、ボツワナ国旗の白と黒の線には、国章に描かれているシマウマの模様もあらわされているともいわれています。
ガンビアの国名について
先住民の言葉で「川」や「堤防」を意味する「gambi」を、15世紀にこの地にやってきたポルトガル人が土地の名前と勘違いしたことに由来する。
ガンビアの歴史(略史)
- 狩猟採集のサン人(ブッシュマン)が住んでいたこの地に、17世紀頃、ツワナ人が住み着き、18世紀にツワナ首長国を建てた。
- 1835年、南からオランダ系移民のブール人が侵入してくると、ツワナ王のカーマ3世はイギリスに保護を求め、1885年にイギリスの保護領ベチュアナランドとなる。
- 1910年には南アフリカ駐在のイギリス高等弁務官(特命全権大使)の管轄のもとに入る。
- 第二次世界大戦後の1962年、カーマ3世の孫のセレツォ・カーマがベチュアナランド民主党(のちのボツワナ民主党)を結成して独立運動を進め、1966年にイギリス連邦内のボツワナ共和国として独立。カーマが初代大統領に就き、複数政党制のもとで政権を握る。
- 多数派の黒人と少数派の白人との融和を進め、政情は安定している。
ガンビアの国データ
| 正式名称 | ガンビア共和国 |
|---|---|
| 英語表記 | Republic of The Gambia |
| 漢字表記 | 岡比亜 |
| 首都 | バンジュール |
| 略号 | GAM |
| 面積 | 1万1300㎢(岐阜県とほぼ同じ) |
| 人口 | 210万人 |
| 通貨 | ダラシ |
|---|---|
| 言語 | 英語、マンディンゴ語、ウォロフ語、フラ語など |
| 民族 | マンディンゴ族、フラ族、ウォロフ族、ジョラ族、セラフリ族 |
| 宗教 | イスラム教、キリスト教、伝統宗教 |
| 独立年 | 1965年にイギリスから独立 |
| 国旗の比率 | 2:3 |
| 在留邦人数 | 3人 |