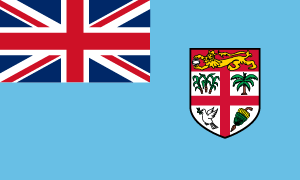バヌアツ
国旗のデザインの由来と意味
赤は生贄にする猪(いのしし)と人間の血を、黒は国民のメラネシア人を、緑は国土の豊かさをあらわします。Y字状の黄色は太陽とキリスト教をあらわし、またこのY字は国土のニューヘブリデス諸島の形をあらわしています。Y字の黄色は最初はなかったのですが、大統領による要望から、メラネシア人をあらわす黒を目立たせるために黄色の縁取りを足したという逸話が伝えられています。
旗竿側に置かれているシンボルは、伝統的に力と富の象徴とされている猪の牙と、平和の象徴、ナメレ(原生シダ)の葉2枚を組み合わせたもの。どちらも古くから宗教儀礼に欠かせない供物(くもつ)として崇められていて、猪の牙は首飾りなどの縁起物にも使われています。ナメレの葉は、かつて聖域への通行許可証の役割も果たしていました。国旗に描かれているナメレの葉は39枚で、これは国会の議席数を示しています。
国旗のデザインは、地元の芸術家カロンタス・マロンによって設計されました。独立を先導したバヌア・アク党の党旗の配色が踏襲されています。
火山の前に槍を持って立つバヌアツの戦士が描かれた、バヌアツの国章。背景には、国旗にも使われている猪の牙とナメレの葉があり、下部にはビスマラ語で「Long God yumi stanap(神と共にあり)」という標語が書かれた黄色いリボンがあります。
国旗と同じく、1980年にイギリスとフランスの共同統治から独立したときに制定されました。
バヌアツの国名について
メラネシア系の言葉「バヌア(土地)」と「ツ(立つ)」で「独立した土地」という意味。18世紀後半、探検家ジェームズ・クックが、スコットランドのヘブリデス諸島にちなみ「ニューヘブリデス諸島」と名付ける。1980年、国名を「バヌアツ共和国」と改め独立。
島々には風変わりな伝統や風習がいまだに残っていて、ペンテコスト島の通過儀礼「ナゴール」とよばれるものは、バンジージャンプのルーツになったと言われています。
バヌアツの国旗の歴史
バヌアツ共和国は、オーストラリアの東に浮かぶ83の島からなる国です。それらの島々は約800キロメートルにわたって連なり、そのうち約70の島に人が住んでいます。
1906年から、イギリスとフランスの共同統治が行われていましたが、1980年イギリス連邦の一員として独立しました。
イギリスとフランスによる、世界で唯一の共同統治領だった頃に使われていた旗がユニークです。
バヌア・アク党率いるバヌアツ人民臨時政府の旗
独立前の1978年、バヌア・アク党によりバヌアツ臨時政府が成立しました。1980年に無事独立を果たし、この党旗の配色をもとに今の国旗が考案されました。
バヌアツの歴史
- 1606年 ポルトガル人が初来航
- 1774年 イギリス人クックが来航し、ニューヘブリデス諸島と命名
- 19世紀前半に白檀(香木)が発見されて交易が盛んになり、宣教師も来島
- クックが来航して以来、ヨーロッパ人による植民が始まったが、イギリスとフランスの間で衝突が繰り返される
- 1906年に両国は、ニューヘブリディーズ諸島を共同統治領とすることに合意
- 1980年 イギリス連邦内の一員の「バヌアツ共和国」として独立
バヌアツの国データ
| 正式名称 | バヌアツ共和国 |
|---|---|
| 英語表記 | Republic of Vanuatu |
| 漢字表記 | 瓦努阿図(略記:瓦) |
| 首都 | ポートビラ |
| 略号 | VUT |
| 面積 | 1万2190㎢(新潟県とほぼ同じ) |
| 人口 | 29万3000人 |
| 通貨 | バツ |
|---|---|
| 言語 | ビスマラ語、英語、フランス語 |
| 民族 | イラネシア系、その他中国系、ベトナム系及び英仏人 |
| 宗教 | キリスト教(プレスビタリアン、ローマカトリック、アングリカン、セブンス・デイ・アドベンティストなど)など |
| 独立年 | 1980年にイギリス、フランスから独立 |
| 国旗の比率 | 3:5 |
| 在留邦人数 | 82人 |